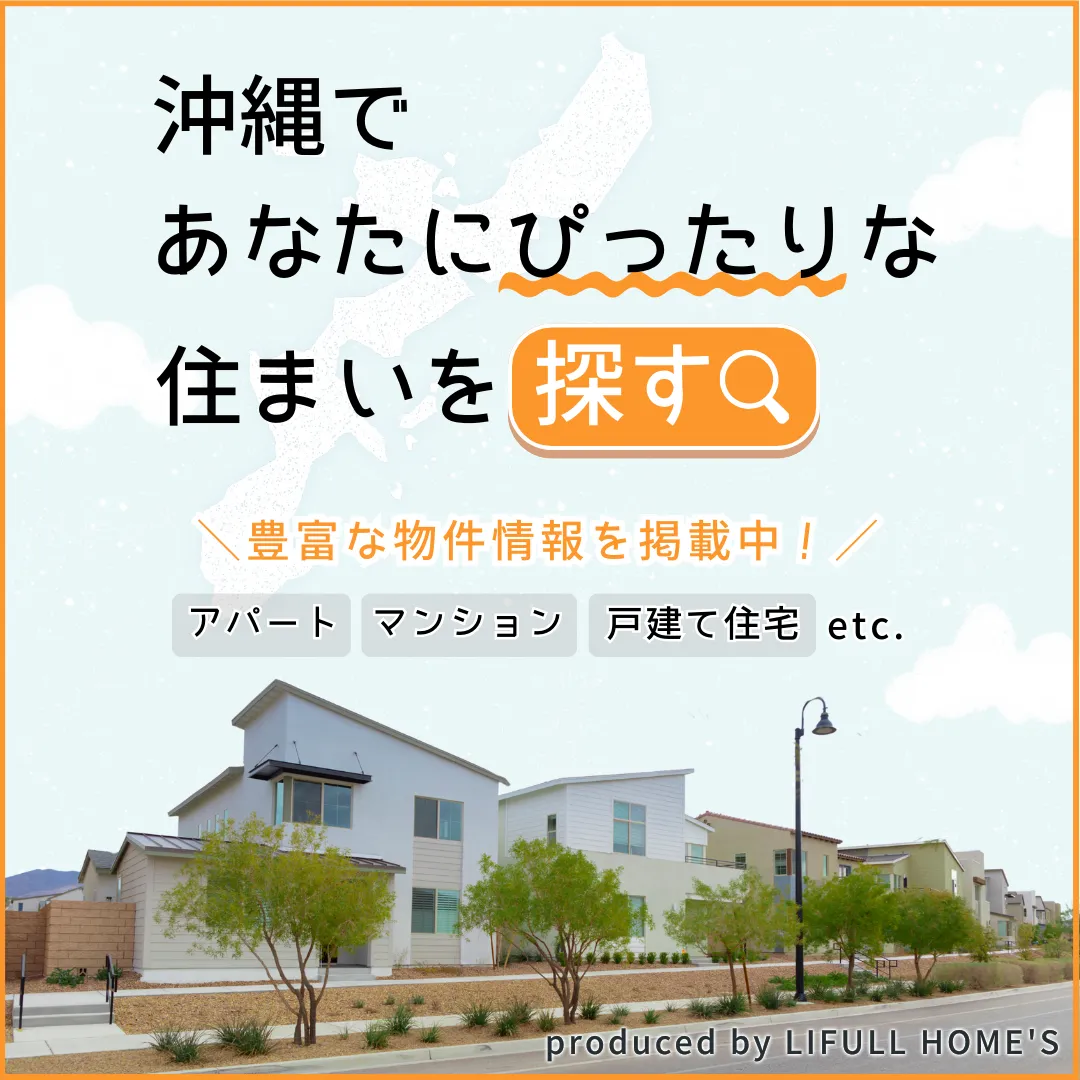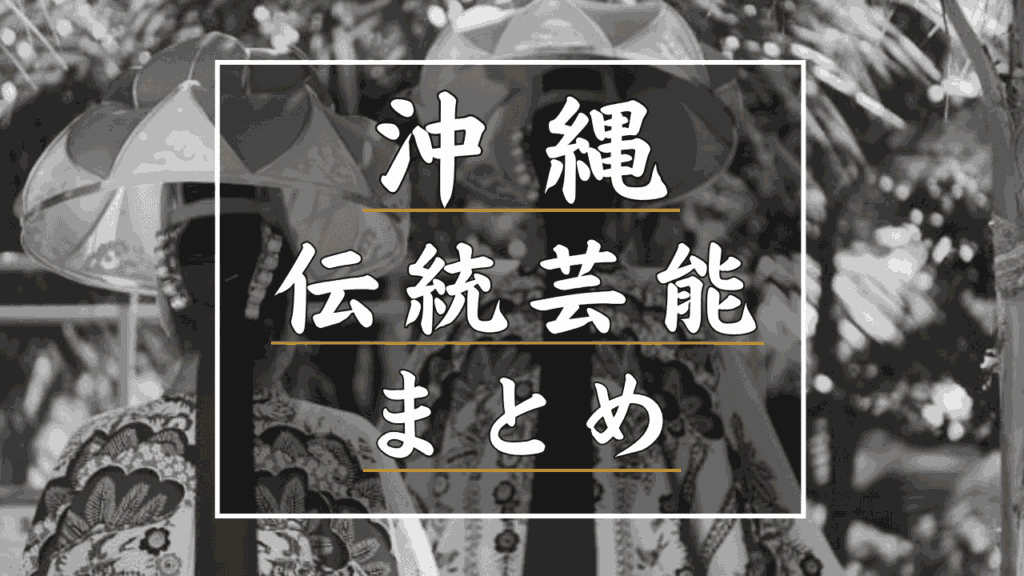
沖縄県には、琉球王国時代から大切に受け継がれてきた多彩な伝統芸能が多く存在しています。
琉球舞踊やエイサー、組踊など、今もなお多くの人々を魅了し続ける伝統芸能は、沖縄独自の歴史や文化を色濃く反映させきました。
本記事では、そんな沖縄の代表的な伝統芸能の種類や特徴、歴史的背景をわかりやすく解説するとともに、実際に体験できるスポットもご紹介します。
沖縄文化に触れたい方や観光を計画中の方は、ぜひ参考にしてください。
沖縄の伝統芸能ってなに?
沖縄の伝統芸能がかつて琉球王国だった頃に、中国や日本、東南アジアの影響を受けながら、琉球王国独自の芸能を作り上げてきました。
また伝統芸能には2種類に分けられ宮延芸能と民俗芸能の2つに分けられます。
- 宮延芸能
宮延芸能は中国からやって来る使いの人達をもてなす歌や踊りで、首里城を中心に行われました。主に組踊や御冠船踊などが宮延芸能として親しまれています。 - 民俗芸能
民俗芸能は、沖縄の各地域の年中行事や祭りの時などに行われるもので、獅子舞やエイサー、民謡などが存在しています。
このように、沖縄では昔から芸能がさかんな地域であることから、芸能の宝庫とも呼ばれています。
琉球王国時代の文化が現代にもしっかりと受け継がれてきました。
沖縄の伝統芸能もまとめて紹介!
ここからは琉球王国時代から受け継がれてきた伝統芸能をまとめて紹介していきます。
琉球舞踊

琉球舞踊は、琉球王国時代の1429年〜1879年に発展した沖縄県独自の伝統舞踊です。
王府文化の古典舞踊と雑踊りという2つの側面を持ちます。
古典舞踊はゆったりと美しい動きが特徴で外交や儀礼のために作られた格式の高い舞踊です。
一方、雑踊りは明るくリズミカルで庶民の生活感ある題材をもとに作られた踊りとなっています。
女性は華やかな紅型衣装と花笠で男性は黒装束でしっかりとした雰囲気で三線や太鼓などの伴奏に合わせて踊るのが一般的です。
組踊

組踊は琉球王国時代の1719年に生まれた沖縄独自の伝統的な歌舞劇です。
組踊は琉球王国の役人であった玉城朝薫が外交時に披露するものとして創作されました。
特徴としては、台詞・音楽・舞踊が一体となった演劇形式で、中国などの使節に披露され外交文化を象徴するものとなっています。
沖縄の古い物語や説話、恋愛物語などが中心で人情味あふれるストーリーで現在もお年寄りからの人気が高いです。
最終的には2010年にユネスコ無形文化財に登録されました。
エイサー

エイサーは沖縄を代表する伝統的な踊りです。
ルーツは15世紀〜16世紀頃を中心に中国を経由して伝わった念仏踊りで時間がたつにつれ太鼓踊りに変化していき現在のエイサーとなりました。
沖縄では9月初めの旧盆になると祖先の霊を慰め送る儀式として長年行われてきており村ごとに独自の型やスタイルがあります。
現代ではダイナミックな振り付けに現代音楽や演出が加わった創作エイサーは観光客や若者にも人気です。
また毎年8月には沖縄県で最大級となるエイサーはのイベント沖縄全土エイサー祭りが開催され3日間で30万人も訪れる大イベントになっています。
棒術

棒術は琉球古武道の一つで長い棒を使い型や組み手を演じる武術です。
もともとは実践的な護身術や戦闘術として発展してきましたが現在は伝統芸能としての側面をもち様々なお祭りや行事で披露されています。
琉球王国時代の1609年では薩摩藩による侵略後は一般民衆が刀剣の携帯を禁止されていたので身近な農具や自己流の武術が発展しておりその中の一つが棒術が有名となりました。
今でも琉球古武道の一分野として体系化され道場や演舞大会で稽古・披露されています。
踊りのように型の美しさ・力強さ・リズム感を目に焼き付けましょう。
沖縄民謡

沖縄民謡は古くから沖縄の人々の生活や自然、心情を歌った民衆の歌です。
主に三線の音色と独特の節回しが特徴的で沖縄文化を代表する音楽として今も多くの人に親しまれています。
生活や日常を歌詞にした独特のリズムと旋律が定番で古くから人気を博しています。
現代でも生ライブが行われていたり明治期以降ではレコードの普及により日本全土でも知られるようになり、20世紀半ばからは沖縄音楽という立ち位置です。
近年は現代ポップスと融合したTHE BOOMやBIGINの影響によりお土産屋や居酒屋では聞かないことありません。
獅子舞

沖縄の獅子舞は日本本土の獅子舞とはルーツや形態が異なる芸能です。
沖縄独自に発展した獅子舞は悪霊払いや五穀豊穣祈願として行われた民俗芸能となっています。
特殊として沖縄の獅子頭が、丸く大きくつくられ赤い舌はなく、愛嬌のある顔立ちです。
また胴体は毛で覆われており中に前足・後ろ足の2人で軽快でダイナミックな動きが特徴として有名です。
太鼓や笛の囃子に合わせて踊り、ジャンプや転がる動きで観客を楽しませつつ、災いを払うとされています。
地元でよく行われている伝統芸能
ここからは比較的観光客には知名度の低い地元で親しみのある伝統芸能を紹介していきます。
旗頭

旗頭は沖縄県独自の伝統芸能で伝統行事の綱引きの際に登場し綱引き文化とともに那覇市や南部で行われています。
旗頭は各地域のシンボルや守り神のような存在の大きな旗を担いで練り歩く壮大な芸能です。
主に祭りで豊年祈願・村、地域の誇り・団結の象徴として現代でも行われてきました。
旗は高さ10m以上の重さは40㎏以上にもなる鮮やかな装飾がされており担ぎ手は力自慢の男性が担ぎます。
また旗はその地域独自の地域名などが書いてあり誇りをもって旗を掲げています。
琉球古典音楽
琉球古典音楽は琉球王国時代の15世紀〜19世紀の宮廷を中心に発展していた伝統音楽の一つです。
14世紀末に中国から伝来した三弦が時期に琉球独自の楽器三線へと変わり琉球古典音楽の伴奏で使用されるようになります。
琉球古典音楽自体も中国・日本・東南アジアの影響を受けながら独自の様式が形成され外交儀式や王府行事で披露され高い格式の音楽となっていました。
現代では沖縄県内の重要無形文化財として保護され国立劇場などでは定期講演があったり観光客向けの酒場でもかぎやで風という音楽はよく耳にできます。
沖縄芝居

沖縄芝居は1829年の廃藩置県により琉球が処分された際に琉球王府で芸能の担い手であった士族が職を失い生計を立てるために町の粗末な芸居小屋で上演をし始めます。
その後1887年に従来の宮廷芸能では飽き足らなくなった観客のために新たなスタイルを始めたのが沖縄芝居です。
上映時間は数分から10分程度の短編作品で歌や台詞、演技に舞踊で基本的に方言で語るスタイルでした。
時代が進むにつれ芝居からテレビへと多様化し方言の理解度も減ったことから少しずつ規模は小さくなっています。
ですが名作や現代人の感覚に合わせた新作品の上演も増加中です。
御冠船踊
御冠船踊は1404年〜1866年の間に22回行われた琉球の伝統的な芸能です。
御冠船踊は特に外交儀式として重要な芸能で、主に冊封使を歓迎するための儀礼芸能として発展してきました。
名称の由来として、御冠船とは中国から正式に王位を認められる「冠」を授かる儀礼に派遣される船で琉球に来ることを歓迎する踊りだったため御冠船踊と名づけられています。
特徴としては大規模なもので数十人もの踊り手が色とりどりの鮮やかな衣装と隊列美が特徴です。
現代でもその形式が受け継がれ琉球古典音楽を基調とした優美な曲に合わせて踊っており、ゆったりとしながら揃った動きが今でも人気を引き続き保っています。
沖縄の伝統芸能を体験できる施設4選
ここからは今までに紹介してきた伝統芸能を初めてでも体験できるスポットを紹介していきます。
観光や学習としてもいい体験ができると思いますので是非体験しに足を運んでみましょう。
体験王国 むら咲むら
体験王国むら咲むらはエイサー・琉舞・カンカラ三線を体験することのできる施設です。
元々NHK大河ドラマ「琉球の風」のスタジオでしたが読谷村に譲渡され現在は体験施設へと変わり活動されています。
体験施設としての評価は高く、1万5千坪の敷地び琉球王国時代の街並みを再現している沖縄県唯一の施設です。
他にも琉球料理を楽しめるレストランや宿泊施設もある観光向け施設となっています。
| 施設名 | 体験王国 むら咲むら |
| 点在地 | 〒904-0323 沖縄県中頭郡読谷村高志保1020-1 |
| アクセス | 那覇空港から車で1時間10分 |
| 営業時間 | 年中無休-9:00~17:30 |
| 体験料金 | 2000円~ ※体験内容によって違い有 |
| 電話番号 | 098-958-1111 |
琉球村
琉球村は沖縄県各地から移築された100年以上の古民家が並ぶ文化体験テーマパークです。
体験内容としては三線稽古や琉装体験や工芸体験など数多くの体験が可能となっています。
またむら咲むら同様に琉球王国時代の住居を再現しているテーマパークとしての立ち位置に定着してきました。
また体験以外に琉球時代の街並みをガイドしたり伝統音楽の生ライブや琉球料理の食堂もあったりと沖縄について深く知ることができます。
全てバリアフリーであったりと誰でも満足のいく施設です!
| 施設名 | 琉球村 |
| 点在地 | 〒904-0416 沖縄県国頭郡恩納村字山田1130 |
| アクセス | 那覇空港から車で1時間 |
| 営業時間 | 通常時9:30~17:00(7月~9月は延長)/年中無休 |
| 体験料金 | 入園料)大人2000円/高校生1500円/小人800円 ※体験時は追加料金 |
| 電話番号 | 098-965-1234 |
美ら笑34CAFE
美ら笑34CAFEはカフェ&バー形式で伝統芸能を体験できるスポットとなっています。
体験内容としては三線体験・エイサー体験・琉装・カンカラ三線制作など幅広い体験が可能です。
比較的規模が小さく体験がメインの施設ではないですが派手過ぎず入りやすい落ち着いた雰囲気のスポットとなっています。
人気店でかつ小規模の店舗の為、訪れる際は予約を忘れずに行いましょう。
| 施設名 | 美ら笑34CAFE |
| 点在地 | 〒901‑0153 沖縄県那覇市宇栄原3‑29‑20 新町テナント2階 |
| アクセス | 那覇空港から車で約10分 |
| 営業時間 | 10:30〜17:00 |
| 体験料金 | 2800円~(体験内容によって値段変動) |
| 電話番号 | 080-1142-3967 |
エイサー会館
エイサー会館は本格的なエイサーを体験できるエイサー専門文化施設です。
高頻度でエイサー会館ではエイサーショーをやっておりエイサーのプロ達が集まっています。
またエイサー体験やショーだけでなく施設の1階では歴史や展示、VR体験などエイサーについて深く知ることが可能です。
エイサー会館に行くだけで手軽に伝統芸能を知ることができる観光におすすめのスポットとなっています。
| 施設名 | エイサー会館 |
| 点在地 | 〒904‑0031 沖縄県沖縄市上地1‑1‑1 コザ・ミュージックタウン1F |
| アクセス | 那覇空港から車で40分 |
| 営業時間 | 10:00~18:00/毎週水曜休館 |
| 体験料金 | 大人300円/小中高生100円/小人無料 |
| 電話番号 | 098-989-5066 |
まとめ
沖縄県の伝統芸能は琉球王国時代の歴史と文化が色濃く残っている文化遺産です。
琉球舞踊や組踊、エイサー、棒術、沖縄民謡、獅子舞などは現代の地域行事や祭りでは深く結びついています。
さらに沖縄県の地元の方に知名度のある芸能も含め多彩さが目立ち、伝統芸能の宝庫と言われてきたことが知れました。
また今回紹介したような体験スポットも複数あり、初心者でも気軽に沖縄の伝統芸能を体験できるスポットも充実しています。
ぜひ沖縄観光を計画している方や伝統芸能、琉球王国について深く知りたい方は是非とも当記事を参考にプランを立ててみてはいかがでしょうか。
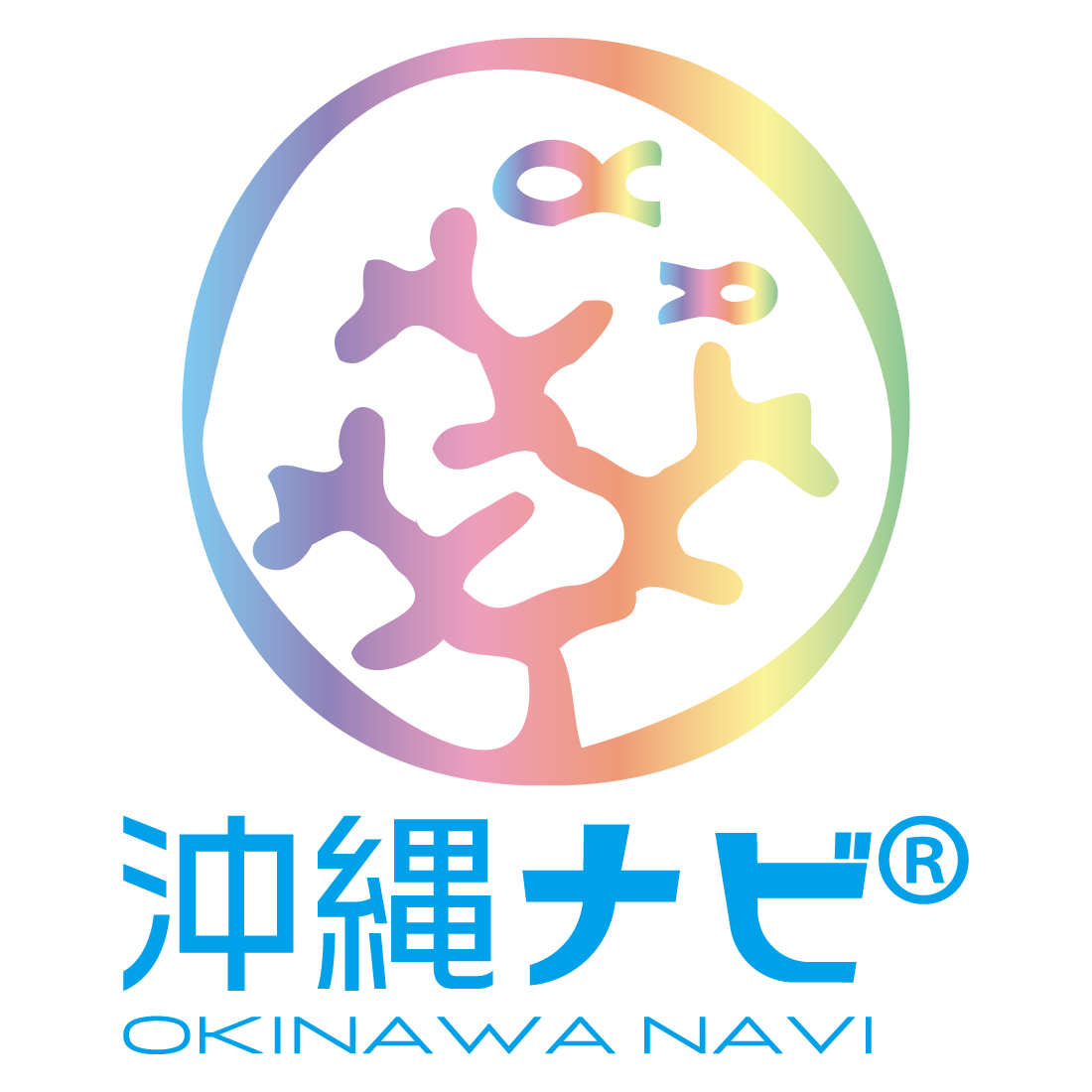
 2025.8.10
2025.8.10