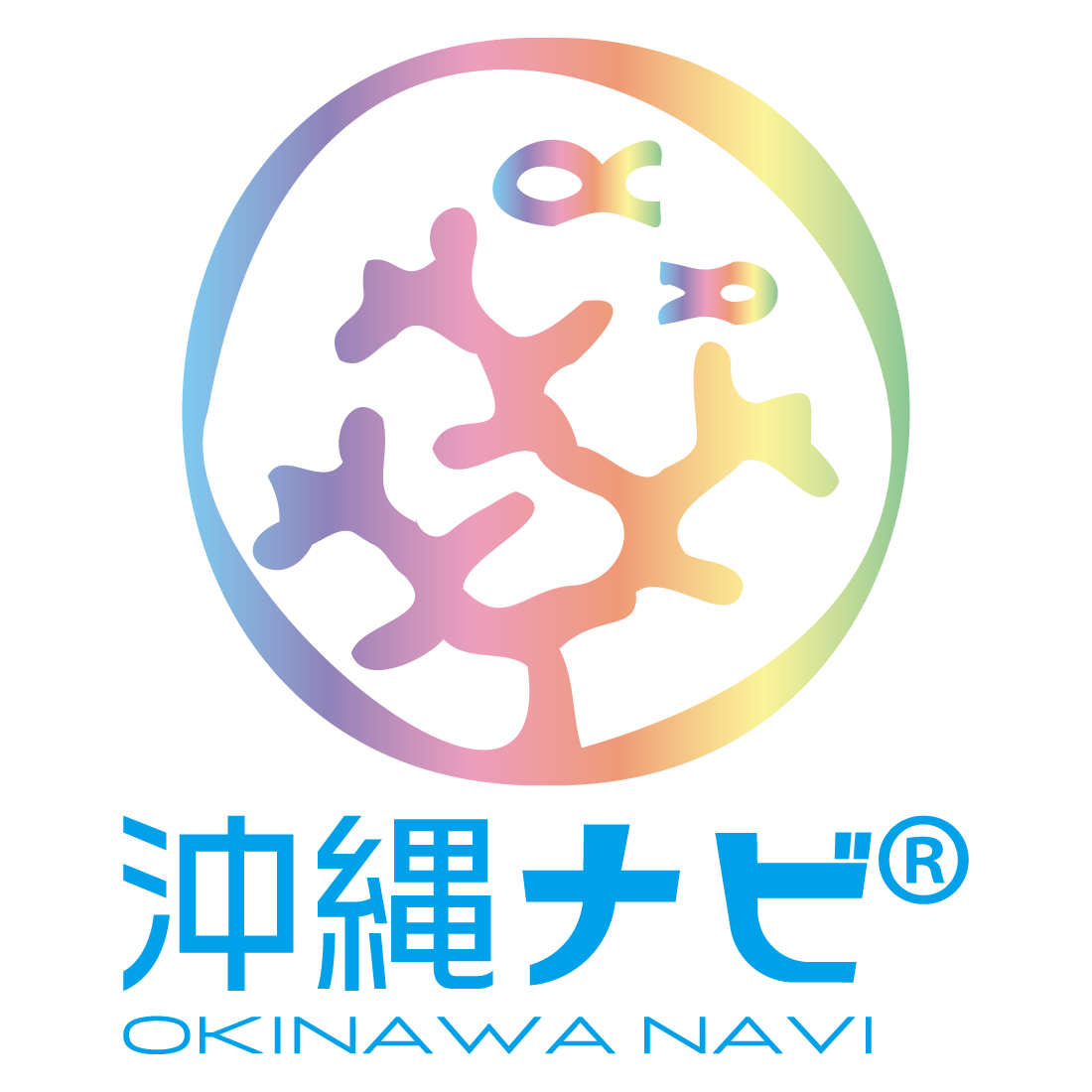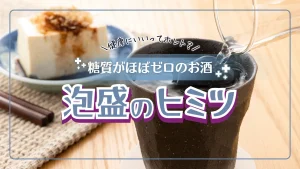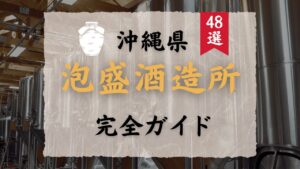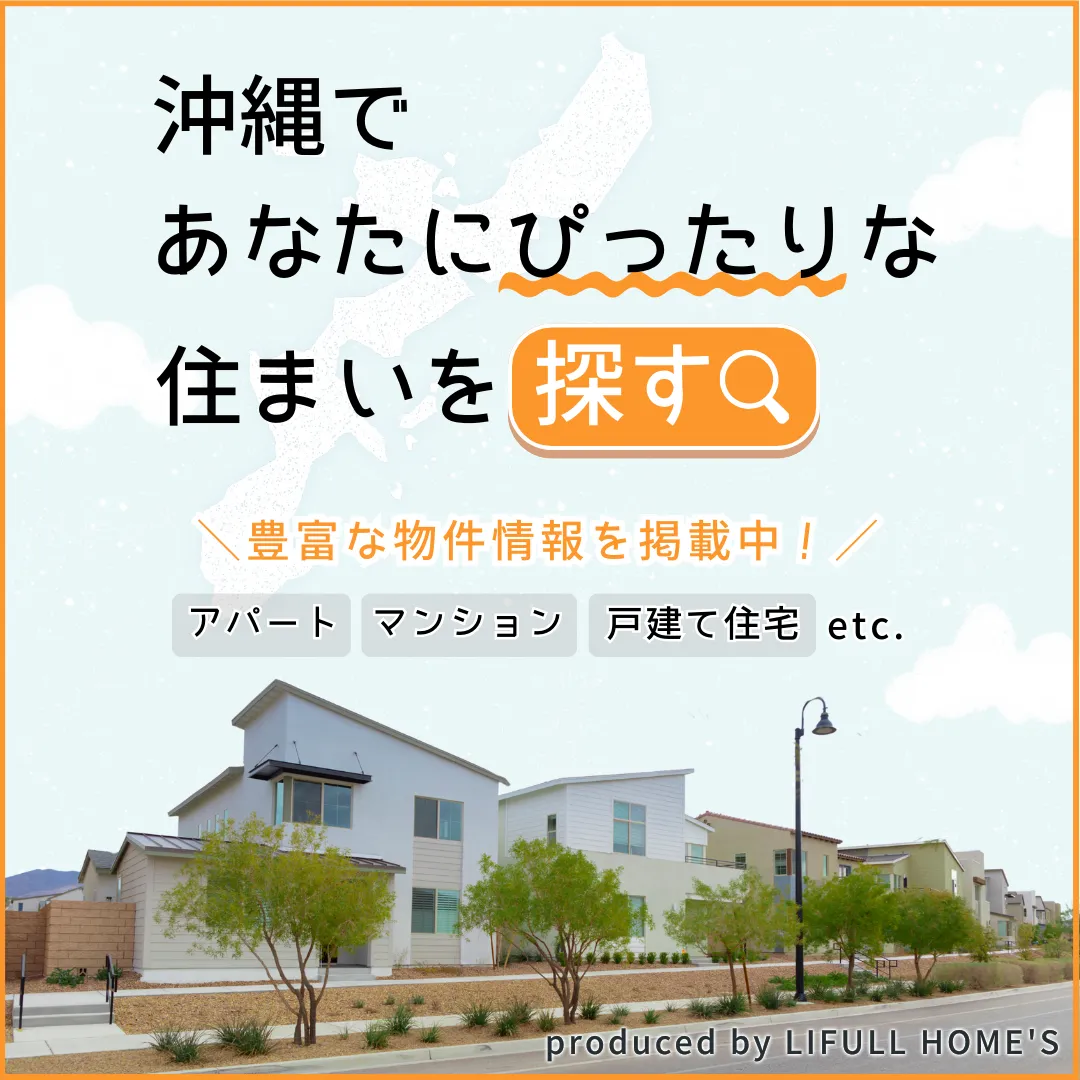2025.12.1
2025.12.1 沖縄のお酒「泡盛」の歴史を解説!日本最古の蒸留酒の魅力と楽しみ方も紹介
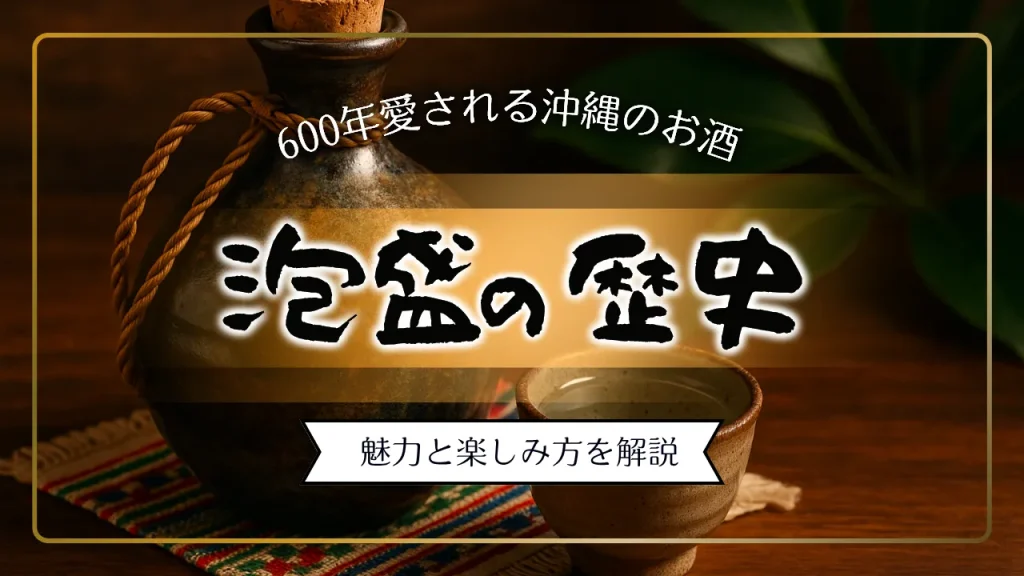
沖縄には、長い歴史のなかで育まれてきた特別なお酒「泡盛」があります。沖縄県内だけで造られている蒸留酒で、日本で最も古い蒸留酒ともいわれています。
600年以上も前、琉球王国の時代にアジア諸国との交流を通じて蒸留技術が伝わり、そこから泡盛の歴史が始まりました。泡盛は、製造方法や原料など、他のお酒にはない特徴がたくさんあります。
この記事では、そんな泡盛の歴史や製造方法、名前の由来、さらには家でも楽しめる飲み方まで、わかりやすくご紹介します。
泡盛をまだ飲んだことがない方にも、その魅力を知ってもらえるきっかけになれば嬉しいです。
泡盛はどんなお酒?
泡盛には、他のお酒とは異なる特徴があります。ここでは、泡盛の特徴や魅力を紹介します。
泡盛の特徴
- 黒麹菌を使用
泡盛は黒麹菌を使用しているのが特徴です。黒麹菌により、深いコクと香ばしさを持つ独特の味わいに仕上がります。 - 単式蒸留機を使用
単式蒸留機を使って蒸留を行います。単式蒸留は一度の蒸留で香味成分をしっかりと残すことができるため、豊かな香りと味わいを保つことができます。
原料はタイ米
泡盛は、タイ産の硬質米を使用しています。長細く粘り気の少ないタイ米は、麹菌を繁殖させやすく、アルコール発酵の際の温度管理も行いやすいメリットがあります。
さらに、発酵によって得られるアルコールの量が多く、泡盛の製造に向いています。現在、沖縄県内のほとんどの酒造所がこのタイ米を使用しており、泡盛の味わいに独特の個性を与えています。
ただし、日本米で泡盛を造ることも可能で、一部の酒造所では日本米を使った商品も販売されています。
古酒(くーす)
泡盛を3年以上熟成させたものを「古酒(くーす)」と呼びます。泡盛は熟成させることで香りがまろやかになり、味に甘みと奥行きが加わります。
かつては100年、200年といった長期間熟成された古酒もありましたが、第二次世界大戦による戦災で失われました。それでも、古酒を守り、育てるための「仕次ぎ(しつぎ)」と呼ばれる伝統的な技術は今も残っています。
これは、年代物の古酒に若い古酒を少量ずつ注ぎ足していくことで、熟成の風味を維持しつつ、お酒を劣化させずに長く継承していく技術です。
この仕次ぎの技術により、ひとつの古酒を世代を超えて受け継ぐことができます。現在、子や孫、さらにその先の世代へ古酒を残していく取り組みが行われています。
沖縄特産「泡盛」の歴史

泡盛は沖縄県で造られている蒸留酒の一種で、日本最古の蒸留酒ともいわれています。
その起源は15世紀の琉球王朝時代にまでさかのぼります。当時の沖縄は、東南アジアや中国との貿易を通じて栄えていた海洋国家で、国際的な交流が盛んでした。
そのような背景の中で、海外からもたらされた蒸留酒やその製造技術が琉球に伝わり、特にタイの蒸留酒文化から強い影響を受けたと考えられています。
蒸留技術は琉球王国の管理のもとで開発され、黒麹菌を用いた独自の製法によって、沖縄ならではの泡盛が生まれました。
当時は、王府から正式な許可を得た酒造所だけが泡盛の製造を許されており、首里城の裏手にある赤田、崎山、鳥堀の3つの地域のみで製造されていました。この地域は、現在でも泡盛の発祥地として知られています。
また、泡盛は外交の場や贈り物としても高く評価されており、薩摩藩や徳川幕府への献上品として用いられたほか、外国からの来賓に振る舞われた記録も残っています。
泡盛の造り方を紹介

泡盛は厳しい品質管理のもと、いくつもの段階を経て造られます。ここでは、原材料の準備から完成までの流れを紹介します。
まず最初に、原料となる米の表面についたぬかを洗い落とし、適度な水分を吸わせるために一定時間水に浸けておきます。
次に、その米を均等に蒸し上げます。この蒸米の工程では、蒸しムラを防ぐために細やかな温度管理が必要です。
蒸しあがった米に黒麹菌が加えて、麹をつくります。ここでは温度や湿度の調整が重要で、泡盛の品質を大きく左右する繊細な作業です。
その後、できあがった米麹に水と酵母を加えてタンクに移し、発酵させてもろみと呼ばれる発酵液をつくります。
もろみが完成すると、蒸留器にかけて蒸留を行い、アルコール度数の高い原酒できます。この原酒はそのままでは風味が安定しないため、専用のタンクで1年以上かけてじっくりと熟成させます。
そして最後に、割り水を加えてアルコール度数を調整し、品質を整えたうえで瓶詰めされます。こうして、泡盛として私たちのもとへ届けられます。
泡盛の名前の由来
泡盛という名前には、いくつかの説が存在します。はっきりとした語源は未だに定かではありませんが、どの説にも歴史的な背景や文化的な意味が込められており、泡盛という酒がいかに長く人々に親しまれてきたかがうかがえます。
泡から来たという説
昔は蒸留したばかりの酒を茶碗や猪口に少量垂らし、その泡立ち具合を見ることで、お酒の出来を判断していたといわれています。
泡が高く盛り上がって長く消えなければ良いお酒とされていたことから、「泡を盛る酒」=「泡盛」と呼ばれるようになったという説です。
粟を使ったことに由来するという説
かつては、泡盛の原料に米だけでなく粟も使用されていました。そこから「粟盛り(あわもり)」が転じて「泡盛」になったという説です。
インドの言葉に由来するという説
古代インドのサンスクリット語に由来するという説もあります。サンスクリット語で酒を意味する「アワムリ」という言葉が、交易を通じて琉球に伝わり、「泡盛」となったというものです。
薩摩によって名付けたという説
江戸時代、琉球王国が薩摩藩を通じて幕府にお酒を献上していた際に、九州の焼酎と区別するために薩摩藩が「泡盛」と名付けた、という説です。
泡盛の楽しみ方は?

泡盛は、飲み方によって香りや味わいの印象が変わります。いろいろなスタイルを試しながら、自分に合う楽しみ方を見つけてみましょう。
定番はロックと水割り
泡盛はアルコール度数が30度前後と高めのものが多く、味や香りがしっかりしています。
その風味をじっくり楽しみたいときは、氷を入れて飲む「ロック」がおすすめです。
一方、食事と一緒に楽しみたいときは「水割り」がぴったり。沖縄では伝統的なスタイルとして親しまれており、水の割合を3〜5割程度に調整しながら自分好みの濃さで味わいます。
炭酸割りも人気
もっと軽やかに飲みたい方には、炭酸で割るスタイルも人気です。
冷やした泡盛と炭酸を用意し、大きめの氷をグラスに詰めて注ぐと、さっぱりとした爽快感が楽しめます。
沖縄らしくシークヮーサーを搾ったり、梅干しを入れたりするのもおすすめです。
ジュースや甘めの飲み物とも相性◎
グァバジュースやマンゴー、バナナなど、トロピカルフルーツ系のジュースとも相性がよく、泡盛の香りと甘みが引き立ちます。
果汁系と混ぜる際は分離しやすいため、軽くシェイクするなどしてしっかりと混ぜるのがポイントです。
泡盛の歴史 まとめ
泡盛は、沖縄で生まれ、長い歴史の中で受け継がれてきたお酒です。黒麹菌やタイ米を使った独自の製法で造られ、香りや味わいに深みがあるのが特徴です。
さらに、熟成させることで「古酒(くーす)」となり、時間が経つほどまろやかさが増していきます。
昔ながらの水割りやロックはもちろん、炭酸や果汁で割って気軽に楽しむスタイルも広がっていて、初めての方にも親しみやすいお酒です。
伝統とともに、今の暮らしにも自然になじむ泡盛。夜の晩酌に、特別な時間のお供に、自分好みの一杯を見つけてみてはいかがでしょうか。